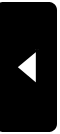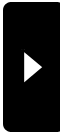10環境塾…ごみから考えるCO2削減⑵
2012年03月10日
2010年11月27日実施
ごみから考えるCO2削減 家庭の省エネ⑵
日時:平成22年11月27日(土)13:30~16:00
場所:明日都浜大津5F 大津市ふれあいプラザ大会議室
省エネ生活の知恵」と題して、3つの体験学習を行いました。

�省エネ生活、得する暮らし方のあれこれ
「最近地球温暖化のことが言われているが、家庭の中でちょっとでも防止できないかということで、エコチェックシートを基本にしての体験をして頂きたい」と、エコライフデー・チェックシートを使っての体験学習がはじまりました。
エコチェックシート25項目の説明を聞きながら、各参加者がシートにふだんの生活態度を思い起こしながら、出来ている項目は〇、ほぼ出来ている項目には△、できていない項目には×を付けていきました。チェックしたあとは、〇(4点)の数と△(2点)の数を数えて合計し、自分の取組み度を計算してみました。(100点満点)その後スタッフがシートを回収、各自のCO2削減量1日量と1年間量を計算して手元に返して頂きましたが、今回参加者の結果はなかなか優秀だったようです。
項目の中でも特に排出量の多いのが、車のガソリンだということがわかりました。徒歩や自転車、公共交通機関を使うのが一番いいのですが、車の乗り方を替えるだけでも省エネになると「エコドライブ10のすすめ」が紹介されました。

現物のごみを目の前にして、分別に挑戦
皆さん『雑がみ』というのをご存知ですか?会場から半分くらいの手が挙がる。だいぶ進歩しましたね。まだまだ生ごみ(燃やせるごみ)の袋の中には、いっぱいの『雑がみ』が入っています。雑がみはきちんと分別してリサイクしてください。
「雑がみ」とは…ダイレクトメール・大小封筒(窓部分のセロファン紙や宛名シールは取り除く)・ハガキ・印刷配布物・案内文書等・テイッシュペーパーの箱(取り出し口のビニールは除く)・大小の紙箱・各種包装紙・トイレットペーパーの芯・カレンダー(金具の部分を取り除く)・紙袋(持ち手が紙以外のもにはそれを取り除く)などを言います。
また、紙の原料にならない禁忌品には…・粘着物の付いた封筒・油紙・ビニールコート紙・紙コップなどのワックス加工紙・裏カーボン紙・感熱紙・金紙銀紙・写真などがあります。これらは家庭ごみに出してください。
一つ一つ具体例を示しながら説明をして頂き、よく分かりました。

「雑がみ」の分別の実際について、古川さんより説明を受けたあと、質疑応答があり、会場からの質問には、黒田紙業の共田さんに応えていただきました。 その後、3グループに分かれての雑がみの分別体験ゲームは大変盛り上がりました。説明を聞いたあとなので、ほぼパーフェクトに分別することができ大満足でした。

腐葉土と段ボールでできる堆肥作り体験
まずはじめに吉田さんより、パワーポイントを使って地球温暖化の成り立ちから、危機に瀕している各国の現状などの報告がありました。話を聞いたあと、実際に作り方活用法を教えていただきました。

【生ごみ処理容器の作り方】
�みかん箱などの丈夫な段ボールの蓋を立て、角と口をガムテープで補強します。
�箱の底に新聞紙1日分を敷いて補強します。
�その中に腐葉土5�と米糠2�を混ぜて箱に入れて発酵床を作ります。
�虫が入らないように網をかぶせ、ゴム紐などで留める。1~2日そのまま寝かすと発酵してくる。(50~60℃に温度があがる)
*段ボール箱の底の通気性を良くするため、下に台を置いて地面から浮かす。木の角材を置いたり育苗箱やカゴを裏返して利用するとよい。
雨の当たらない軒下やガレージに設置すると良い。できるだけ、風通し日当たりの良い場所に置くこと。

【使い方】
�生ごみは2~3�位に小さく切り、微細目の三角コーナーに入れて水気を切る。
�生ごみと米糠を混ぜる。1回投入量の目安200~500g程度。ごみ500gに米糠一握り、
�段ボールの発酵床、生ごみを入れる前に全体に良く混ぜる。
�発酵床を堀り、生ごみを入れ発酵床とよくなじませ、投入場所の上に少し盛る。
�虫除けの網をかぶせる。
�翌日も�~�の手順で繰り返す。
【箱がいっぱいになったら】
�箱がいっぱいになったら、新しい箱に古い方の発酵床を3/1位入れ、それを床にする。
�古い床は温度が上がらなくなるまで湿度を保ちながら良く切り混ぜる。大体10日位で発酵が止まるので、止まったらそのまま1ヶ月ほど寝かせる(熟成)堆肥ができました。
*堆肥の保管は米の紙袋(通気性あり)が効果的
熟成後に家庭園芸に利用。そのままでも利用できるが、一度ふるいに掛けると良い。ふるいに残った固形物は、再度発酵床に戻すとよい。
出来上がった堆肥でこんなに立派な野菜ができました。

ごみから考えるCO2削減 家庭の省エネ⑵
日時:平成22年11月27日(土)13:30~16:00
場所:明日都浜大津5F 大津市ふれあいプラザ大会議室
省エネ生活の知恵」と題して、3つの体験学習を行いました。

�省エネ生活、得する暮らし方のあれこれ
おおつ環境フォーラム エネルギー学習研究グループ 塚尾さん
「最近地球温暖化のことが言われているが、家庭の中でちょっとでも防止できないかということで、エコチェックシートを基本にしての体験をして頂きたい」と、エコライフデー・チェックシートを使っての体験学習がはじまりました。
エコチェックシート25項目の説明を聞きながら、各参加者がシートにふだんの生活態度を思い起こしながら、出来ている項目は〇、ほぼ出来ている項目には△、できていない項目には×を付けていきました。チェックしたあとは、〇(4点)の数と△(2点)の数を数えて合計し、自分の取組み度を計算してみました。(100点満点)その後スタッフがシートを回収、各自のCO2削減量1日量と1年間量を計算して手元に返して頂きましたが、今回参加者の結果はなかなか優秀だったようです。
項目の中でも特に排出量の多いのが、車のガソリンだということがわかりました。徒歩や自転車、公共交通機関を使うのが一番いいのですが、車の乗り方を替えるだけでも省エネになると「エコドライブ10のすすめ」が紹介されました。

現物のごみを目の前にして、分別に挑戦
おおつ環境フォーラム 雑がみおよび紙分別とリサイクルPJ 古川さん
皆さん『雑がみ』というのをご存知ですか?会場から半分くらいの手が挙がる。だいぶ進歩しましたね。まだまだ生ごみ(燃やせるごみ)の袋の中には、いっぱいの『雑がみ』が入っています。雑がみはきちんと分別してリサイクしてください。
「雑がみ」とは…ダイレクトメール・大小封筒(窓部分のセロファン紙や宛名シールは取り除く)・ハガキ・印刷配布物・案内文書等・テイッシュペーパーの箱(取り出し口のビニールは除く)・大小の紙箱・各種包装紙・トイレットペーパーの芯・カレンダー(金具の部分を取り除く)・紙袋(持ち手が紙以外のもにはそれを取り除く)などを言います。
また、紙の原料にならない禁忌品には…・粘着物の付いた封筒・油紙・ビニールコート紙・紙コップなどのワックス加工紙・裏カーボン紙・感熱紙・金紙銀紙・写真などがあります。これらは家庭ごみに出してください。
一つ一つ具体例を示しながら説明をして頂き、よく分かりました。

「雑がみ」の分別の実際について、古川さんより説明を受けたあと、質疑応答があり、会場からの質問には、黒田紙業の共田さんに応えていただきました。 その後、3グループに分かれての雑がみの分別体験ゲームは大変盛り上がりました。説明を聞いたあとなので、ほぼパーフェクトに分別することができ大満足でした。

腐葉土と段ボールでできる堆肥作り体験
市民・生ごみリサイクルプロジェクト 吉田さん
まずはじめに吉田さんより、パワーポイントを使って地球温暖化の成り立ちから、危機に瀕している各国の現状などの報告がありました。話を聞いたあと、実際に作り方活用法を教えていただきました。

【生ごみ処理容器の作り方】
�みかん箱などの丈夫な段ボールの蓋を立て、角と口をガムテープで補強します。
�箱の底に新聞紙1日分を敷いて補強します。
�その中に腐葉土5�と米糠2�を混ぜて箱に入れて発酵床を作ります。
�虫が入らないように網をかぶせ、ゴム紐などで留める。1~2日そのまま寝かすと発酵してくる。(50~60℃に温度があがる)
*段ボール箱の底の通気性を良くするため、下に台を置いて地面から浮かす。木の角材を置いたり育苗箱やカゴを裏返して利用するとよい。
雨の当たらない軒下やガレージに設置すると良い。できるだけ、風通し日当たりの良い場所に置くこと。

【使い方】
�生ごみは2~3�位に小さく切り、微細目の三角コーナーに入れて水気を切る。
�生ごみと米糠を混ぜる。1回投入量の目安200~500g程度。ごみ500gに米糠一握り、
�段ボールの発酵床、生ごみを入れる前に全体に良く混ぜる。
�発酵床を堀り、生ごみを入れ発酵床とよくなじませ、投入場所の上に少し盛る。
�虫除けの網をかぶせる。
�翌日も�~�の手順で繰り返す。
【箱がいっぱいになったら】
�箱がいっぱいになったら、新しい箱に古い方の発酵床を3/1位入れ、それを床にする。
�古い床は温度が上がらなくなるまで湿度を保ちながら良く切り混ぜる。大体10日位で発酵が止まるので、止まったらそのまま1ヶ月ほど寝かせる(熟成)堆肥ができました。
*堆肥の保管は米の紙袋(通気性あり)が効果的
熟成後に家庭園芸に利用。そのままでも利用できるが、一度ふるいに掛けると良い。ふるいに残った固形物は、再度発酵床に戻すとよい。
出来上がった堆肥でこんなに立派な野菜ができました。

Posted by Satoyamahozen at 00:57│Comments(0)
│環境塾
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。